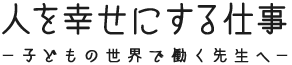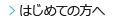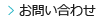私が幼稚園のコンサルタントを始めたのが2005年。
その頃の幼稚園は2年保育入園と3年保育入園があり、2年保育入園が減少している頃でした。
3年保育入園数が伸びていたので、3年保育入園の園児数を
できるだけ多くすることが園経営の最重要ポイントになっていました。
多くの幼稚園は、入園後の至れり尽くせりの過剰サービス化
(バスで自宅前に送迎する、お弁当給食で親が弁当をつくらなくてよい等)
と未就園児教室を中心にした園児募集力向上によって、
他園との激しい競争に勝って園児数を増やしていました。
以前2年保育入園が減少したように、3年保育入園数が減少しています。
私の経験則になりますが、幼稚園のコンサルティングをはじめた頃は、
年少150名募集で総園児数450名を達成するのが難しい状況でしたが、
5年後には年少100名募集で総園児数300名を達成するのが難しくなり、
現在は240名でも難しくなっています。200名前後の園が増え、
地域によっては120~150名前後の園児数になっています。
そして、幼稚園の競合は幼稚園や認定こども園だけではなく、
働く女性が増えたことで保育園とも競合しています。
待機児童が減少している地域は、保育園と競合している傾向が顕著に現れ、
待機児童が少なくなるのに合わせて幼稚園の園児数が減少します。
待機児童がいる時は、保育園に入れなかったから幼稚園に入園していたと推測されます。
保育園は1才2才で入園するため、幼稚園も2歳児の受け入れ体制を強化してきました。
多くの園が満3歳入園と週一回親子分離で登園する
プレクラス型未就園児教室の2つを展開していると思います。
今までは、満3歳園児数とプレクラス園児数の合計が年少目標園児数の90%くらいを占めて、
3年保育入園の一般募集枠をできるだけ少なくする園が、いい園児募集結果を出していました。
しかし、これも無償化によって状況が大きく変わります。
無償化が始まる前は、プレクラスの人数が2歳児全体の7・8割を占めて、
満3歳入園(毎日2歳児クラス)は1・2割くらいでした。
無償化が2019年10月から始まり、プレクラスの保育料が満3歳入園よりも高いという現象が起こりました。
保育園・認定こども園3号2歳園児の保育料が満3歳になっても無償化にならないことも影響し、
満3歳入園希望者が増えて、プレクラスと3年保育園児が減少しています。
1号認定園児の満3歳無償化の影響は大きく、
ご両親が働いていても通える体制を整えている幼稚園や認定こども園に
保育園から転園希望するご家庭も増えています。
恐らく2021年度も3年保育入園園児数は減少し、
そして幼稚園と認定こども園1号認定の満3歳園児が増えるでしょう。
(保育園・こども園の3号認定は1歳入園が増えています。)
今後は、幼稚園と認定こども園は1号認定の満3歳入園(毎日2歳児クラス)の園児数を増やして、
年少の目標園児数と同じくらいにしていく必要があります、
例えば年少目標数100名なら、満3歳(毎日2才クラス含む)入園園児数は最低70名以上、
できれば80~90名にした方がいいでしょう。
年少と満3歳園児数を同じくらいにするために
年少以上の園児数を減らして、3学年180名の園を
3学年150名+満3歳30名=180名の園にする場合もあります。
※低年齢児の受け入れを増やすことは、教員・保育者の数を増やすことにつながります。
(1・2歳の園児6~7人に対して一人の教員・保育者の配置が必要)
教員・保育者を配置できないために、全体の園児数を減らす選択をする園も、今後増えるでしょう。