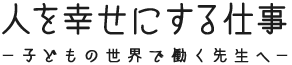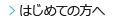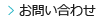子ども子育て支援新制度・保育料無償化・新型コロナ禍などによって、
社会が大きく変化している今、人気園の在り方が変化しています。
以前の人気園は園児数であり、園児が多いほど人気がある園と言われてきました。
園児を増やすための保護者満足度を高める取り組みを、積極的に拡大してきたと思います。
しかし保護者満足度を高める取り組み
(バス、預り、給食、保護者に見せるための発表会・運動会など)は、
時に教職員の長時間労働につながり、働く教職員の負担になりました。
そして幼稚園はハードで長年継続して働くことができないというイメージを定着させました。
現在は11時間開園・土曜日開園などで園の開園日時が
より長期間・長時間になり業務内容がよりハードになっています。
教員を採用することができず、教員がいないために園児を受け入れることができない園、
教員が少ないのに多くの園児を受け入れて評判が悪くなる園など、
園児を増やすことによって人気がなくなる事例が出てきました。
現在は園児数が多いことではなく、園児数と教員数が適正になっていることが
人気園になるために最低限必要です。適正とは園児数に対して教員の数が多い状態のことです。
教員1名辺り約10~11人の園児数が適正です。
教員数が多いことが優先で、さらに人を育てることができる優秀な教員が多くなると
人気園になります。(優秀な教員が豊富にいる園という認知度向上も必要)
※教員=幼稚園教諭・保育士の免許を取得している人
園児数と“優秀な”教員数の適正化を実現するためには、教育目標だけではなく、
目標教職員数と目標平均勤続年数(勤続年数を長くする目標)と
教職員一人ひとりの成長目標を組織で共有し、勤続年数を長くして退職を少なくし、
人を育てることができる教員が多い園になることが必要です。
収支差額を増やして教職員の生活を豊かにするために、
決算目標(園の収支差額)を共有して、
収支差額を最大化する取り組みを実施することも必要です。
新制度園で収支差額を最大化するためには、利用定員数と園児数が同じであること、
園児数に対して教員を手厚く配置して満3歳6対1加算やチーム保育教諭加算等の加算が
全て適用されることが必要です。(加算が適用されると収入が増えます。)
私学助成の幼稚園で収支差額を最大化するには、
園児数を増やすか無償化保育料以外の特定負担金の増額が必要です。
そして経費をできるだけ少なくすることで収支差額は最大化します。
しかし、少子化と競合園数の増加によって、園児数を増やすことは年々困難になっています。
また新制度の園を中心に、他園が手厚い教員体制になっていること、
多様化している園児の状況や教員の仕事能力が業務内容に追いつかない状況から、
人件費などの経費を減らすことは難しい状況です。
(教員数を少なくすることは新たな人気園の在り方ともずれます。)
したがって私学助成幼稚園で収支差額を最大化するには、特定負担金を増額するしかありません。
(もしくは別事業で収支差額を増やし、園に資金移動して投資する)
人気園に両制度で共通するのは、人を育てることができる教員の数が多いことです。
しかし最も大きな課題は“人を育てることができる教員の不足”です。
※人を育てることができる教員の定義
自分の知識と経験を提供しながら、世の中で生きていく為の武器と、
自立して幸せな人生を歩く力を教え子に与えることができる人
人を育てることができる教員数を増やすためには、教職員の退職が少ない職場、
そして成長できる職場になることが必要です。退職が少ない職場になるためには、
長時間労働をなくす業務の時短化と残業申請制度・有給消化の仕組みが必要です。
※残業申請制度とは?
教職員からの残業申請を元に上長が必要性を判断して、許可を出せば残業できる制度。
(認められた残業の残業手当は発生する。)
成長できる職場になるためには
教職員のキャリア形成をサポートしなくてはいけないのですが、
園内園外問わず教職員の学びの機会が減少していないでしょうか?
新型コロナ禍によって、園内研修も園外研修も減少しています。
また、新2号認定・2号認定園児が増えて、午後に残る園児の数が増えました。
しかし、早朝・夕方に勤務できる非常勤教員(パート教員)の雇用は困難で、
正規教員がシフト制で早番・遅番勤務をしています。
シフト勤務によって全員が集まる機会が少なくなり、
時間を創り出してスケジュール化しないと園内研修ができません。
WEB(ズーム等)を使った講師による外部研修もありますが、
組織を育てるためには実際に集まって教職員同士がコミュニケーションを取り、
一人一人の知識と経験を共有する園内研修が必要です。
全員で同じことを学び、同じ目標を共有して目標達成にチャレンジし、
結果検証を繰り返すのが園内研修です。
園内研修によって組織の意識が同一化し、同じ言葉・志で話ができるようになります。
教職員が成長できる職場になるために、園内研修を実施しましょう。
退職が少なく成長できる職場を、経理・人事や研究開発・調達等の
各部門・機能が連携して支えることで、園児が成長し収支差額が最大化します。
収支差額を最大化できれば、教職員の育成や教育・保育・職場の環境整備に
再投資することができます。そして園が成長します。
今後少子化が進むことで必要な教員数が少なくなり、
教員採用難は解消するという人もいます。
確かに子どもの数は減りますが、同様に人口も減少し高齢化が進み、
労働人口が減少します。(国の予測:2030年800万人の労働人口不足)
また、教員不足の根本的な原因は『先生になりたい!』という人が少ないことにあります。
先生になりたいという希望者が少ないことを解決しないと、
少なくとも2030年まで教員不足は続くでしょう。
採用強化という話になるのですが、採用は
定着(退職が少ない職場)と育成(成長できる職場)がセットです。
そして、そのような職場であることが学校や学生に伝わらないと採用できません。
“どうやって採用するのか?”よりも、そもそも職場が
「ここで働きたい」と思える職場になっていることが必要です。
働きたい職場になっているのかを厳しい目で確認し、必要があれば職場改善を実施しましょう。
そして、自園の職場を多くの人に知ってもらう広報活動を実施しましょう。
広報活動によって、安全に安心して働くことができる、
仕事にやりがいがあり成長できる職場であることが伝わります。
そして、ここで働きたいという人が集まってきます。
職場改善と職場の広報を実践して、働きたい人が自然に集まってくる状態を実現しましょう。
“集める”のではなく、“集まってくる”ようになることがポイントです!
退職が少なく成長できる職場づくりと広報を通じて、
人を育てることができる教員が多くいる組織を実現しましょう。
そして、人気園であり続けましょう。